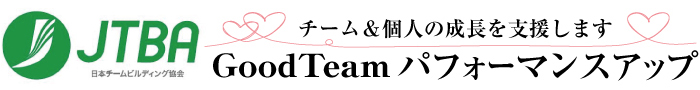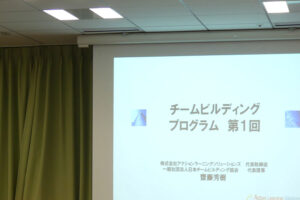タックマンモデル第3段階・ノーミング(標準期)で最も重要なこと
第3段階のチームや組織が一般的にたくさんあれば学習する機会がありますが、現状はチーム成長プロセスの第1段階(フォーミング:形成期)か第2段階(ストーミング:混乱期)のチームや組織ばかりです。第3段階(ノーミング:標準期)を経験しているリーダーはごく少数です。
せっかく第2段階を突破できても第3段階を経験していないリーダーは今まで経験したことのないマネジメントを行う必要があるため、大方のリーダーは戸惑ってしまいます。
第3段階、第4段階まで経験したリーダーは道筋を考えることができるますが、今の状態だけをマネジメントしてアウトプットだけを変えるのはハッキリ言って不毛です。
これをやってしまうと・・・
チーム・組織のメンバー、誰もよくなりません。
チームビルディングをきちんと学び、どの状態にチーム・組織を成長させていくことが望ましいか、ゴール設定がきちんとあり、現時点の場所からゴールに向かって進んでいくにはどのようにステップアップしていくのか設計することが重要です。
必ずしも設計通りにはなりませんが、羅針盤がなければゴールとは別の方向に進んでいってしまいます。
ひとまず、チームビルディングを体系的に学び、実践を積み重ねて、チーム・組織の成長とはどのようなことなのか感じてください。
第3段階の終わり頃から始まっていくこと
タックマンモデルの第3段階・標準期(ノーミング)に入り、チーム・組織が醸成されていくと成功体験を積むための階段を登っていきやすくなります。
ここで重要なことは個人のエネルギーを溜めること、自分とチームに対する信頼感のエネルギーを溜めることです。
出来たという自信・事実で個人のエネルギーを溜める
チーム・組織がうまく機能せず、車のガス欠のような状態になっている要因は「褒められる」「些細なことで喜んでくれる」ことが少ないことが起因となり、一人一人が『自信』を持てないでいます。
誰も喜んでくれない…
無表情の人が多い…
自己承認されることがない…
このような場では支え合う心が薄いため
「このチームすごいよね!」
「このチームなら出来るよね!」
というようなチームに頼ったり信頼するマインドセットができません。
リーダーはメンバーが行動してやってのけた事実を一緒に喜んでエネルギーを溜めて高め合っていきましょう。
自分とチームに対する信頼感のエネルギーを溜める
チーム・組織に頼れる段階になるとシナジーが生まれやすくなり、精神的な「気持ち」としての信頼感ではなく、アウトプットを出して成果に対する「本当に出来る」という信頼感になります。
この状態が続いていくとものすごい変化があり
「このチームなら何でもできる!」
という言葉が出るようになります!
このチームなら達成感を持ってより大きな成果を出せる!
という自信と絶大な信頼感が出てきます。
このことが当事者意識として「自分の責任」と「主体的に取り組む姿勢」を加速させ、次の4段階へ進むためのエネルギーになります。
第3段階(ノーミング)でマイルストーンを細かく刻みながら進む先にあること
リーダーが掲げた目標に対して
「我々は実績を積んできたので、その目標は達成できます!我々に目標を決めさせてください!」
という非常に前向きでやる気に満ちた発言がメンバーから出てきます。
リーダーが牽引してきた流れから「自分たちで考えて行動する」メンバーが自立していく流れに変わっていきます。
チーム成長のネックはメンバーの自立性にある
第1段階や第2段階のように自立性が低い場合はメンバーが勝手な判断でトンチンカンな方向に行ってしまわないようにチームリーダーが上から諭していくことが必要になります。
トップダウン型の組織でも本来はチームメンバーの育成が目的ですが、上から押さえつけてしまうマネジメントをしているリーダーが多いです。
圧力をかけてコントロールをしてしまうと育成になりません。
リーダーは段階により依存させるのではなく自分で考えて行動できるようにポジションを変えていかなければなりません。
成功体験のプロセスを踏んでいく中で出てくる社会性のスイッチ
チーム・組織の目標は売上を上げることだけではありません。
日本チームビルディング協会では下記のような内容を研修でお伝えしています。
仕事は自分を成長させる道具です。
会社は社会に貢献するための道具です。
目的は社会に貢献することで、様々な活動の中から自分の強みも活かして貢献しながら生活していることが本来の姿です。
仕事をすることで「やりがい」や「貢献欲求」が満たされていき幸福感と繋がっていきます。
社会性のスイッチが入ると単純な売上目標ではなく自分たちの仕事や自分たちのチーム力を通じて
- まだ業界でやっていないことにチャレンジしてみよう!
- 世界に通用することをやってみよう!
- 自分たちの技術で●●で困っている人の役に立とう!
など、どのようにしたら社会の役に立てるのかを真剣に考えて取り組んでいきます。
成長している企業は社会の役に立っており、ミッション・ビジョンを具現化するチーム・組織が世の中を牽引しています。
売上や利益は価値に対しての成果・効果のため結果論になります。
価値・成果・効果、何に貢献していくのか分からずに売上・利益だけを目標にしてしまうと当然ですが仕事が不毛な作業になっていきます。
リーダーはこの部分に向き合い、きちんと考えていかなければなりません。
まとめ
個人の幸福度は仕事を通して社会の役に立つことで上がっていきます。
リーダーは是非、社会性についても真剣に向き合い、GoodTeamを目指してください。