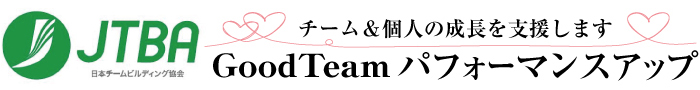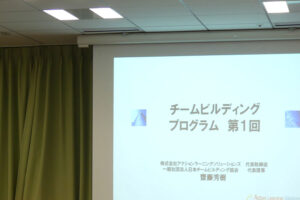変化しないチームがたどる道
第2段階の混乱期(ストーミング)へ進むルートは複数あります。
当たり前のことですがチームに対して何もせず放ってしまうと第2段階へ進まないので成長することはありません。
日本チームビルディング協会で様々なチームビルディング研修を行ってきた結果、チームビルディングを学んでいない状態では、第1段階の形成期(フォーミング)から第2段階の混乱期(ストーミング)へ進むことはほぼ不可能です。
チームが自然と好循環のサイクルになっていくことはほぼありませんが、唯一あるとすれば人間の本能的なことになりますが危機感を持った人が集まり自己組織化していくことです。
自分たちで変化していくことができる時だけ自然と形成期から混乱期へと移行していきます。
世の中は常に変化し変化しかありませんが、企業が変化をしていかない原因としては下記のようなことがあります。
- 働いている人たちに危機感がない
- 自分の人財的価値に気づいていない
- うちの会社は大丈夫だ、という根拠のない自信
企業やチームが井の中の蛙であり、ゆでガエルの状態であると変化を望めません。
日本人の傾向としてリーマンショックの時もそうでしたが、潰れそうになって奮起するのではなく潰れてから奮起することが多く、日本において危機管理がさほど機能していないのは「自分たちは大丈夫」という根拠のない確信、心理が働いていると思います。
会社内で危機感を持つのではなく、新聞やニュースを見て知る人が多い現状です。
企業がマズいことは社員に言わない傾向があるため、体質として危機感を持ちにくい状態になっていることが見受けられます。
最悪な状態にならないと変容が起こらないことがほとんどです。
個人商店の集団が最悪な状態になった時、何が起こるのか?
第1段階の個人商店の方々は他人と協働せずにずっと個人でやってきたにも関わらず自分に自信を持っている人は稀です。また、自分の力を出して組織を立て直そう、チームを良くしていこうとしようと思っていないですしできるとも思っていません。
生き詰まってどうにかしなければいけない時、その時だけ瞬間的にみんなでどうにかしようとベクトルが自分ではなくお互いに向くことがありますが、外部要因で一時的に出てきたテンションのため、意見は言いますが自分で行動しようとする人がいない状態となります。
口だけ出して行動しない評論家集団の誕生です。
評論家集団の特徴として、地頭がいいため意見を言うことができます。
崖っぷちにいるため危機感をエネルギー源として色々な発想ができます。
ところが・・・
自分で責任を取りたくないことから本気度が低くやる気がないため、「●●が良いと思う」「こうやったらどうですか?」「誰かやりなよ!」というような意見はたくさん出ますが言うだけになってしまいます。しかも、会議の時間が長く、誰が何をやるのか、みんなやりたくないので結論を出さないで終わります。
危機的状況の中で何も行動をしないと本当に会社が潰れてしまうため、これを見かねたポジションパワーを持っている社長や部長などのリーダーが評論家集団が議論していた意見を無視して「●●でやろう!」と権限を行使し決めてしまいます。
そうすると評論家の方々は「どうせ社長(部長)が勝手に決めるんでしょ…」「意見を言っても意味ないね…」と振り出しに戻ります。
多くの企業がこれを繰り返しており、最終的にモノを言わない集団となっていきます。
自分たちで何かを変えられると思っていませんし、意見を言っても無駄だと思っています。
その中で不満だけはくすぶっています。
特に若手がそのようになっている傾向が見受けられるので注意が必要です。
多様性を活かすのがチームビルディングですが、逆の方向となってしまっているため、これでは本物のチームにはなれません。
モノを言わない集団が続いていくと・・・どうなっていくか?
評論家集団がモノを言わない集団になり、これが続いていくと・・・
ずばり、モノを考えない集団になります。
自分たちの課題なのに外部のファシリテーターが介入して課題を浮き彫りにすることがよくあります。
当事者なのだから色々なアイデアがあるはずですが、アイデアが何も出てこない・・・
日常の中で考える習慣がないと想像力・創造性を使っていないので、いざという時に発揮されません。金属と同じで段々と錆びついていった状態です。
さらに、リーダーが絵に描いた餅の理想論や根拠が明確でない計画を立ててしまうことでメンバーは盲目的にやっているだけとなります。
これらのことから第1段階と第2段階を行き来しながら衰退していくパターンが多くみられます。チームが成長不全のため、チームが機能するように「あり方」というガソリンを入れなければなりませんが、戦略や方法論など言葉だけ入れ替えて外見のボディを磨くようなやり方ばかりをしていると第1段階と第2段階を行き来するだけになってしまいます。
ガソリンがなければエンジンをかけることができないということです。
日本チームビルディング協会の検証では本来のチーム力が発揮される第3段階の標準期に進めない企業が多いことが分かっています。
最終的に手に負えなくなったチームの末路
崖っぷちにいるのに本質的なテコ入れせずに前身してしまい芳しくない状態が続いてガタガタになった手に負えないチームは最終的に経営層が組織の再編とリストラをして立て直そうとします。
それでもダメな場合は売却、M&Aとなります。
手に負えないチームとなってしまった原因として、資源は人のため人が成長していくマネジメントをしていなかったことです。
日本の企業では「人」への投資が少ないです。
人を資源・財産ではなくコストと見ていると成長していきません。
経営層は「人」に投資をしてチームが成長し成果を継続的に出していけるチームを作ることが求められています。
まとめ
まずは現実におきている事実を理解してください。
日常は大変だと思いますが、自分がいるチーム(組織)がどのような場所になっているか振り返ってみてください。
振り返ることで何かしらの「気づき」が得られます。気づきから変化していくことが可能です。
リーダーや経営層の方々は昭和のやり方を踏襲するのではなく、令和の時代に合った日本本来のあり方をベースにしたマネジメントを学びGoodTeamを目指してください。