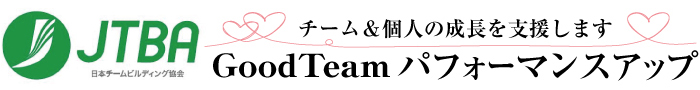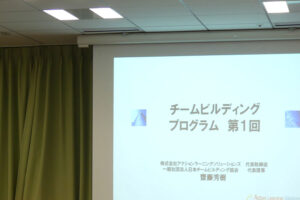目指す場所・目標について全員が腹落ちしているチームは強い
チームが個人商店化する原因は明確な目標がないことと目標が腹落ちしていなくモチベーションに繋がっていないことです。第2段階で評論家集団になってしまったチームの原動力は危機感であるため想像力や創造性のスイッチが入りません。このような組織ではタックマンモデルの第2段階・混乱期(ストーミング)を乗り越えることはできません。
本来は第2段階でスパッと意見を言い合う関係が望ましいです。結果を残したオリンピックの団体戦やサッカーのワールドカップ、高校野球の甲子園などの例をみると「金メダルを取りたい!」「優勝したい!」とチームの目標が明快です。尚且つ、原動力がモチベーションのため全員が金メダルを取りたい、優勝したいと思っています。
この状態は本気度が高く、モチベーションで動いているので創造性のスイッチが入っており、全員から意見が出る機能するチームとなっています。
自分が達成したいこととチーム全員が達成したいことが同じことでシナジー(相乗効果)が生まれやすい環境が整います。
チームが何かを成し遂げるために最も重要なことは目標が明確なだけでなく定義が具体的で腹落ちしていることである
船が出航する時は目的地が示されています。目的地がなければ大海原で船が航海している時にどこへ行くのか迷ってしまいます。これと同じで、どこに向かっているのかチーム目標が明確なだけでなく腹落ちしていなければなりません。腹落ちの度合いは一人一人の中にある琴線に触れる何かが必要となります。
例えば、ある人は社会貢献の欲求や意識が強かった場合、「この仕事が社会の何に役立てることができるのか」「どのような人に喜ばれたり感謝してもらえるのか」この仕事の先に色々な人たちが見えて良い姿のイメージが強いと俄然やる気になります。
このような欲求や意欲は万人の共通なものでありますが、一人一人性質が異なっているため全員が同じではなく差はあります。
「勝ちたい」という欲求や意識が強い人の場合、「勝つ」とは
- 誰と戦っているのか?
- どのような状態を勝つというのか?
この2つがハッキリ理解できないと「勝つ」という状態があやふやだと、やってもやっても勝っている実感は出て来ません。
戦っている相手が企業であれば、生産性や利益率など色々あります。
社会問題やまだできていない領域であれば、どのような状態になったら勝っているといえるのか、具体的な定義を組織のリーダーだけではなくチームメンバーで考えていくことが必要です。
腹落ちしていると動機が明快なのでモチベーションになります。
本気度が高いので全員からアイデアが出て、「誰が言ったのか」は関係なく目標に一番近づけるアイデアを出した人が尊重されます。さらに行動するのが早く、たとえ一瞬うまくいかなくても誰かの責任にすることはなく修正してまた行動するため成果が出やすい状況を生み出していきます。
しかし、「評論家集団の末路、チーム成長の第2段階・混乱期で機能しない組織へ向かう残念な話」でお伝えした第2段階で評論家集団になってしまった場合はチームメンバーが「何を言ったか」よりも社長や部長など「誰が言ったか」の方が影響力があり、ポジションパワーを持った人が言ったことに対して「そうですよね」と言って責任を影響力のある人に向けます。
さらに評論家集団は議論だけしていて本当にやろうと思っている人がいないので「やりましょう」と次の行動に進まず、しかも誰も責任を取らないような体制を作り上げて回避しようとする傾向があります。
このような大人を見ている若手はリーダーになりたいと思わなくなるので、パーソル総合研究所「グローバル 就業実態・成長意識調査( 2022 年)」の調査でも明らかになっているように企業家やリーダーになりたい若者が少ない国になってしまっています。
ここが評論家集団で責任を取りたくない組織と目指す場所・目標と定義がしっかりしていて本気度とモチベーションが高い組織との差となります。
売上や利益は結果でしかないため具体的な定義にならない
今のビジネスの一番重要なポイントは自分たちが作り上げた社会的価値によって生み出された結果が売上だと考えます。
- どれだけ多くの人に喜ばれたのか
- 恩恵を感じてもらえたか
- 感謝してもらえたか
この結果が数値として表れた のが売上や利益です。
極端なことを言うと何の価値も生み出していないのに売上が上がっている企業はブラック企業である場合が多いと思います。
若者は近くにいる大人の背中を見て育っていくことは昔から変わらない
「親の背中を見て育つ」ということわざは「子は親の鏡」のことわざと同じとみなされています。上司となる人たちは、どのような姿勢で仕事をしているか問われます。背中が美しくないと追随する人たちは現れません。リーダーになっていく若者が現れないと企業活動が続かず衰退していきます。
時代は変化していますが、昭和のやり方で仕事をしている企業が多くみられます。
そのため、日本の多くの企業は第1段階の形成期(フォーミング)、第2段階の混乱期(ストーミング)にいるためチームがうまくいかないのは当たり前のことです。
特にリーダーは気づいて変革していく努力が求められています。
まとめ
目指す場所・目標について全員が腹落ちしていていくことが重要で、意見・アイデアを出し合い「自分がやる」意思を持って行動に繋げることが第2段階の混乱期を乗り越えていくポイントです。本質以外の部分に時間を割かないようにすることも重要です。
日本チームビルディング協会では、チーム力はタックマンモデルの第3段階・標準期(ノーミング)からしか生まれないと提唱しています。
必ず通る混乱期を恐れずに次の第3段階・標準期(ノーミング)へ移行しGoodTeamへと進んでいってください。