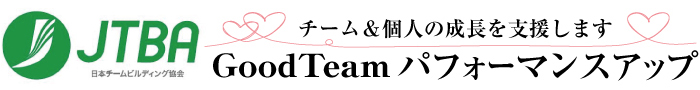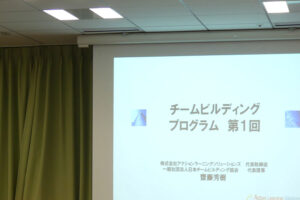みんなでやってみよう!となって初めてベクトルが合う
日本チームビルディング協会が提唱する本来のチーム・組織はタックマンモデルの第3段階である標準期(ノーミング)からとなります。
意見やアイデアを出し、時にはぶつかり合いながら第2段階・混乱期(ストーミング)を見事に突破できると第3段階の標準期(ノーミング)に入ります。
ここで初めてシナジー(相乗効果)が生まれていきます。
日本の企業のほとんどが第1段階の形成期か第2段階の混乱期にあるため、第3段階の標準期に入った企業は素晴らしい会社になっていることがほとんどです。
ただし、第3段階・標準期のマネジメントが課題となってきます。
リーダーが経験したことがない第3段階・標準期のマネジメント
第3段階・標準期のマネジメントをやったことがないリーダーがほとんどである理由は簡単で、今までのリーダーは標準期と混乱期にしかいたことがないからです。
第1段階と第2段階にいる個人商店の方々はルーティンワークの仕事をしていて自立性が低いことが多く、トップダウンのマネジメントで仕事をしているため指示待ちかリーダー依存になります。また、そのようなマネジメントしかみたことがなく、されたこともないため、第3段階の当事者意識が強く自立性で動く組織についてやったことがありません。
自立性の本質は目標に対するコミットメント、本気度になります。
全員が目標に向かって拘りを持ってチーム内に存在します。
成果に本気度がある場合のみ、当事者意識が芽生えています。
本気度は目の色や表情、使っている言葉で分かります。
そのため、緊張感の中に目標達成に向けて進んでいる雰囲気があるチーム(組織)とすぐに伝わります。
このような当事者意識があり本気度が高く、目標に対してコミットメントしているチームのマネジメントをしたことがないリーダーは今まで第1段階と第2段階で受けてきたマネジメントをやってしまい、「いくぞ!売上前年の2倍!」「前年度の20%アップ!」など根拠が不明確で過去やってきたことを踏襲してしまう傾向があります。
そのため、目標の意味を見出すことはできず、チームビルディングの観点からチームの状態に合わない過度な目標設定をしてしまうと下記2項目が現れます。
- どうせ無理と諦めてしまう
- 他責・他力になる
誰かが何とかするだろう、自分がやらなくても大丈夫だろう、リーダーだけやればいいのでは、というような感じで、マネジメントするリーダーが目標設定を間違えてしまうとチーム・組織は第1段階か第2段階に戻ってしまいます。
「あり方」というガソリンが入っているチーム・組織でないと第3段階ではパフォーマンスを発揮できない
自分たちが本当に達成可能な目標について一歩目の階段・目標地点(マイルストーン)はどこですか?
この問いに対して、信頼関係と本気度の要素を作ってきたチーム・組織でない場合、リーダーの顔色を伺います。このレベルではパフォーマンスを発揮できません。
信頼関係と本気度の要素を作れていると安全な場があるため「●●はできると思います」と素直にリーダーへ言えます。また、一歩目が達成できるチーム・組織は機能します。一歩目の階段を上り、二歩目・三歩目の階段も一歩目と同じように上るため同時にパフォーマンスもよくなっていきます。
マネジメントの手法、やり方だけを切り取ってやろうとするリーダーがいますが、安全な場が確立されていないので当然うまくいくことはありません。
今までのマネジメントはいきなり高い目標を掲げて絶壁を作りチームメンバーの尻を叩きながら早く登れと鼓舞することが多くみられたと思います。登れないメンバーは根性が足りないと精神論で何とかしようとする傾向が強かったと思います。
しかし、一人一人実力の違いはあります。強みも異なります。
価値を出していかなければ企業の存在意義がありません。
チーム・組織・一人一人が登れる階段を作るのがリーダーの仕事であり、令和の時代に求められるマネジメントであります。
そのためには「あり方」という根がしっかりあり、お互い認め合いながら意見やアイデアを遠慮なく言い合える「安全な場」が醸成されていることが必須となります。
まとめ
過去の踏襲で仕事をしていても成果が出ない時代です。リーダーも意識改革が必要で「あり方」というガソリンが入っているチーム・組織にして、目標を明確にし中間地点の目標を置きながら階段を上っていくようなイメージでチーム・組織だけでなく一人一人に合った成長曲線を提示できるようリーダーが行うマネジメントを再構築していきましょう。